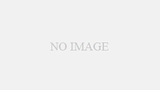「在宅ワーキングホリデー」という言葉をご存知でしょうか。
ここ数年でSNSや検索ワードに頻出するようになったこの言葉は、実は2024年頃から急激に注目を集め、月間検索回数は一時10万件を超えたともいわれています。
「好きな場所で暮らしながら働ける」「海外に行かなくてもワーホリ気分が味わえる」など、多様な口コミが飛び交い、特に20〜40代の女性を中心に関心が高まっているようです。
その一方で、「怪しい」「うまくいかなかった」という声も少なくありません。
制度の内容や運営団体の信頼性、収入面の実態など、多くの人が“メリットとリスクの間”で揺れながら、情報を探している状況です。
なかでも注目されているのが、在宅ワーキングホリデー協会という団体と、代表の安田真菜さんの存在です。メディア出演や講演活動も増えており、制度としての“顔”を担っていると言えるでしょう。
本記事では、実際の口コミや制度の仕組みをもとに、在宅ワーキングホリデーという新しい選択肢の「中身」を丁寧に読み解いていきます。
必要以上に肯定も否定もせず、体験談とデータを通じて、読者の皆さまが冷静に判断できる材料をご提供することを目的としています。
「在宅で働けて、自由に暮らせる」──その言葉の裏には、どんな現実があるのでしょうか。
その答えは、これから見ていく口コミの中にあります。
「自分に合う働き方に出会えた」 ──前向きな口コミから見える魅力
「初めて月3万円、自分の力で稼げたんです。こんな感覚は初めてでした」
「自宅で仕事ができるだけじゃなく、全国の仲間と交流できたことが、いちばんの財産かもしれません」
こうした声は、在宅ワーキングホリデーの体験者による実際の口コミの一部です。
SNSやインタビュー記事では、クラウドワークやオンライン講座を通じて、徐々に収入を得られるようになったという報告が複数見られます。
特に目立つのは、「スキルゼロでも始められた」という安心感や、「人とのつながりが生まれた」という意外な副産物への評価です。
また、在宅ワーキングホリデー協会では、案件紹介やスキル学習の場を提供するだけでなく、“小さな成功体験”を積み重ねるサポートに力を入れているとされています。
その影響もあってか、「最初の仕事をやりきったことで自信がついた」「もう一度挑戦してみようと思えた」といった前向きな変化を語る口コミも少なくありません。
もちろん、収入の面では個人差があります。
ですが、月1〜3万円の副収入を「生活にちょうどいいプラスα」と捉え、自分のペースで続けているという利用者も一定数存在します。
単に稼ぐ手段というよりは、「自分のための働き方をつくるプロセス」として活用されている印象です。
在宅ワーキングホリデーという仕組みは、決して万能ではありません。
けれど、一部の人にとっては確かに、「今の自分にちょうどいい」働き方の選択肢となっているようです。
そのことは、静かに語られる体験談の中に、確かに残されています。
変わったのは、働き方だけじゃなかった ──“肯定の声”が語る小さな変化
「お金のために始めたけど、一番大きかったのは“時間”が戻ってきたことでした」
「“働くこと=消耗”だと思っていたけど、少しだけ考えが変わったかもしれません」
こうした声は、収入そのものよりも、心の変化に焦点を当てた口コミの一部です。
在宅ワーキングホリデーを通じて、働き方そのものに対する認識が変わったという報告も、少なくありません。
たとえば、時間の自由度。
朝から夕方まで会社に縛られる生活から、「自分のペースで仕事ができる日々」に移ったことで、家族との時間が増えたり、自分自身と向き合う余裕ができたと語る人もいます。
また、スキルの有無にかかわらず、誰かから仕事を任され、それをやりきったという経験は、小さな成功体験として強く心に残るようです。
「最初は“自分なんて無理”と思っていたけど、やってみたらちゃんとできた」という声も多く、自己肯定感の回復にもつながっている様子がうかがえます。
そして意外にも多いのが、「孤独感が減った」という声です。
在宅であっても、同じような立場の人とつながれる環境が用意されていたことで、誰にも頼れなかった日々から一歩踏み出せたという体験談が語られています。
もちろん、こうした変化はすべての人に起こるわけではありません。
けれど、在宅ワーキングホリデーという選択肢が、ただのお金稼ぎではなく、「暮らし方」や「働き方」の問い直しにつながっているのは、間違いなさそうです。
「思ったより稼げない」は本当?──よくある誤解と注意点
在宅ワーキングホリデーに関する口コミのなかで、もっともよく目にするネガティブな声のひとつが、「思ったより稼げなかった」というものです。
この背景には、「数ヶ月で本業以上に稼げる」といった過度な期待や、働く仕組みへの理解不足があるように見受けられます。
たとえば、在宅ワーホリで紹介される案件の多くは、クラウドワークやコンテンツ制作、接客業務など、多様ですが即高収入に直結するものではないケースも多いのが実情です。
実績やスキルの蓄積に応じて少しずつ報酬が増える仕組みであるため、「最初の数ヶ月は収入が少ない」という声は一定数存在します。
しかし、それは「稼げない制度」ではなく、「成長と積み上げの構造を理解せずに始めてしまった」ことが要因である場合も多いようです。
在宅ワーホリ協会の代表・安田真菜さんは、こう語っています。
「“最初から稼げる”というイメージが独り歩きしてしまうことがあります。でも、本当は“育てていく働き方”なんです。焦らず、自分のペースで動ける方ほど、結果が出やすい傾向があります」
また、「孤独を感じやすい」「自己管理が難しい」という声もありますが、それらも事前に知っておくことで対策が取れるリスクです。
協会では定期的な面談や学習サポート、仲間同士のチャットグループなどを通じて、ひとりで抱え込まないための工夫がなされています。
つまり、在宅ワーキングホリデーには注意点があるのは事実ですが、「制度が悪い」のではなく、「理解せずに飛び込んでしまった」ことが原因でつまずくケースが多いというのが、実際のところです。
知らなかったから失敗した。
でも、知っていれば、防げることもある。
そう思わせてくれる口コミが、少しずつ増えてきています。
「向いている人」とは、じつは“特別じゃない人”かもしれません
在宅ワーキングホリデーに向いているのは、どんな人でしょうか。
そう聞かれると、「パソコンに強い人」「時間に余裕がある人」「特別なスキルを持っている人」と考えがちかもしれません。
けれど、実際の体験談や口コミを見ていくと、そうしたイメージとは少し違った人たちが活躍していることに気づきます。
たとえば、こんな人たちです。
- 決められた時間にきっちり働くのが苦手だけど、自分のペースなら続けられる
- 子育てや介護、家の都合で「まとまった時間がとれない」と感じている
- 「いきなり何かを始めるのは怖いけど、小さくなら挑戦してみたい」と思っている
- 生活を大きく変えたいわけじゃないけれど、「ちょっとでも前に進みたい」と感じている
つまり、向いている人の特徴は、「今の自分を否定せずに、今の場所から動いてみたい」と思えるかどうか──それだけなのかもしれません。
安田真菜さんも、こう話しています。
「在宅ワーキングホリデーは、何かを“変える”というより、“広げていく”働き方だと思っています。自分の中にある小さな余白を、どう使うか。それを一緒に考えるのが、私たちの役割です」
特別じゃなくていい。
変わろうとしすぎなくてもいい。
ただ、「少しでも自分らしく働きたい」と感じている人にとって、この仕組みは新しい選択肢になり得るのかもしれません。
「自分のペースで働く」という選択肢があっても、いい
在宅ワーキングホリデーという言葉に、最初は少し戸惑いがあった方もいらっしゃるかもしれません。
「本当にそんな働き方があるの?」「怪しくないの?」──そんな不安の声も、実際に多く寄せられています。
でも、その一方で、実際にこの制度を使って新しい一歩を踏み出した人たちの、静かな肯定の声もまた、確かに存在しています。
・育児のすきま時間を使って、初めて収入を得た主婦の方
・本業だけでは満たせなかった「自分の時間」を取り戻した社会人の方
・「やってみたら、自信がついた」と語った20代の女性
彼らが語る言葉には、大きな成功ではなく、日常のなかで自分を少しずつ取り戻していった軌跡があります。
「稼げるかどうか」だけでなく、「どう働きたいか」「どう生きたいか」という問いに向き合う中で、この仕組みを選んでいる人もいます。
もちろん、簡単なことばかりではありません。
最初からスムーズに収入が得られるわけでもなければ、手厚い指導がつくわけでもありません。
でも、「無理なく、でも本気でやってみよう」と思えたとき、支えてくれる土台があるという点では、在宅ワーキングホリデーはひとつの安心材料になり得るのだと思います。
代表の安田真菜さんが語る「自分の余白をどう使うか」という言葉は、今の私たちにとってとても象徴的です。
忙しさや不安のなかにいると、「今のままで大丈夫だろうか」と思う瞬間があるかもしれません。
けれど、自分の中にほんの少しでも「変わりたい」「試してみたい」という気持ちがあるのなら、それを大事にしてあげていいのだと思います。
在宅ワーキングホリデーは、派手な制度ではありません。
けれど、「自分のペースで、無理せずに始められる働き方がある」という事実を知るだけでも、これからの人生の選択肢が少し広がるのではないでしょうか。
今すぐ始めなくても構いません。
でも、「知っている」ことは、いつかのタイミングで、あなたを助けてくれるかもしれません。
その日のために、そっと記憶の引き出しに入れておいてください。